松前道広は江戸時代中期に蝦夷地を治めた松前藩の第8代藩主です。12歳で家督を継ぎました。蝦夷地統治に情熱を注ぎました。
ロシアの通商要求を拒否、クナシリ・メナシの戦いを鎮圧するなど、北の守りを固めることに尽力しました。でも、その一方で派手好きで浪費癖があり藩の財政を悪化させたり、反幕閣との交流も盛んでした。
隠居後も蝦夷地への強い執着を見せ、幕府から長期間の謹慎を命じられます。
2025年の大河ドラマ「べらぼう」では、えなりかずきさんが松前道広を演じ史実よりも誇張された残虐な人物像が描かれ注目を集めています。
この記事では松前道広の波乱に満ちた生涯や、彼の型破りな素顔について詳しく解説します。
名前:松前道広(まつまえ みちひろ)
どんな人?
- 名前:松前道広(まつまえ みちひろ)
- 別名:源助章広幸広外記
- 生年月日:宝暦4年1月17日(1754年2月8日)
- 没年月日:天保3年6月20日(1832年7月17日)
- 享年:78
家族
- 父:松前資広(まつまえ すけひろ)
- 母:弁子(八条隆英の娘)
- 妻・正室:敬姫(たかひめ)知子(花山院常雅の娘)
- 側室:平田氏
- 子:松前章広(まつまえ あきひろ)、蠣崎広匡(かきざき ひろまさ)など。7男6女。
松前家の家紋
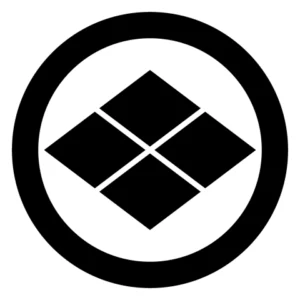
松前家の家紋:丸に割り菱
松前氏
松前氏のルーツは蝦夷地(現在の北海道)の豪族、蠣崎氏(かきざきし)にあります。
室町時代に道南に点在した「道南十二館」の一つ花沢館主の蠣崎季繁(すえしげ)は長禄元年(1457年)のコシャマインの戦いで客将の武田信広(たけだのぶひろ)の活躍もあり勝利。蠣崎氏は蝦夷地における和人(アイヌでない日本人のこと)社会の支配者となりました。
信広は季繁の婿養子になって蠣崎氏の家督を相続したといいます。家伝によれば武田信広は若狭武田氏の一族と言いますが真偽は不明。

武田信広の肖像画
その後の当主たちは樺太への影響力拡大や安東氏からの自立、奥州諸大名との婚姻による連携で戦国大名としての地位を築き上げました。
文禄2年(1593年)。蠣崎慶広(よしひろ)の代に豊臣秀吉から蝦夷地支配を安堵され、慶長4年(1599年)に松前氏と改姓しました。
1600年(慶長5年)に福山城を築城。そのため福山藩とも呼ばれます。
1604年(慶長9年)には徳川家康から蝦夷地支配を認められました。米がとれないため無高でしたが、水産物や獣皮の交易、徴税で財政を賄いました。
当初は正式な大名ではなく交代寄合でしたが、1719年(享保4年)に1万石格に。しかしロシア艦の来航増加により、1799年(寛政11年)と1807年(文化4年)に蝦夷地が幕府直轄領となり、陸奥国梁川へ移封され9000石となります。
1821年(文政4年)に蝦夷地は返還されて1831年(天保2年)に再び1万石格、1849年(嘉永2年)には城主大名となりました。
松前道広の生い立ち
松前道広は宝暦4年1月17日(1754年2月8日)に生まれました。
父は松前藩主の松前資広。
道広は長男です。幼いころから学問や武芸に優れた才能を発揮していました。でもその一方で非常に派手好きで、時には傲慢な態度をとることもあったと言われます。周囲の人は大変だったでしょうね。
明和2年(1765年)10月。父・資広の死去により、わずか12歳という若さで家督を継ぐことになりました。まだ幼い彼が広大な蝦夷地を治める藩主となったのです。この若さでの藩主就任は周囲の人々は期待とともに不安もあったでしょう。
従五位下志摩守への叙任
藩主となった松前道広は10代将軍 徳川家治に謁見しました。そこで彼は従五位下志摩守に叙任されます。これは当時の大名にとって非常に重要なことで、幕府から正式に藩主として認められた証だったのですよ。
蝦夷地統治への並々ならぬ情熱!松前道広の功績とは?
松前道広の治世は松前藩が蝦夷地における支配体制を強化し、北からの脅威に対応する上で、極めて重要な時期だったと言われています。
ロシアへの強硬姿勢!一体なぜでしょうか?
当時、ロシアは蝦夷地との通商を強く求めていました。これは松前藩にとって、幕府にとっても大きな脅威となっていました。松前道広は、このロシアからの通商要求に対し断固として拒否する強硬な態度で臨みました。当時の日本は鎖国政策をとっていましたから、道広も幕府の意向をよく考えて蝦夷地の防衛体制の強化に力を注いだそうです。彼自信も北の守りに対しては強い思いがあったようです。
クナシリ・メナシの戦いと、その後の影響は?
寛政元年(1789年)、国後島(くなしりとう)と目梨(めなし)地方でアイヌによる大規模な反乱「クナシリ・メナシの戦い」が起こりました。この反乱は松前藩の厳しい支配や、和人(わじん)との不公平な交易が主な原因とされています。
松前道広はこの報告を受けると、すぐに新井田正寿(にいだ まさとし)や松井広次(まつい ひろつぐ)らを派遣、速やかに反乱を鎮圧させました。この戦いは松前藩のアイヌ政策に大きな見直しを迫るきっかけとなります。また、後の幕府による蝦夷地直轄化へと繋がる非常に重要な出来事でもあったのです。
財政窮乏!松前道広の私生活とは?
松前道広はその功績の一方で、非常に個性的な私生活を送っていました。
反幕閣との交流!その影響とは?
彼は当時の幕府とは距離を置いていた一橋治済(ひとつばし はるさだ)や伊達家(だてけ)、島津家(しまづけ)といった反幕閣の人物たちと積極的に交流しました。また幕府から警戒されていた国学者(こくがくしゃ)の高山彦九郎(たかやま ひこくろう)とも親交を結んでいます。
道広は幕府に素直に従うだけでなく、不満も持っていたようですね。でも、同時に幕府から警戒される結果にも繋がったことでしょう。
贅沢な遊興と藩財政の悪化!
彼は派手好きな性格だったので遊興で大量の出費をしました。吉原の遊女を妾にするなど、その浪費は藩の財政を大きく圧迫してしまいます。
結果として松前藩は商人からの多額の借金を抱えることになったのです。この散在ぶりには、幕府も黙っていられず。何度か幕府から注意を受けました。藩主としての責任を問われる場面も少なくなかったようですね。
隠居後の波乱!謹慎と蝦夷地への尽きぬ執着心
寛政4年(1792年)10月。松前道広は長男の章広(あきひろ)に家督を譲り隠居しました。でも、隠居後も彼の行動力は衰えることはありません。彼は大炊頭(おおいのかみ)、後に美作守(みまさかのかみ)と名を変え、影響力を持ち続けました。
イギリス船プロビデンス号事件での行動は?
寛政8年(1796年)。イギリス船プロビデンス号がアプタ沖(現在の北海道虻田郡洞爺湖町)に出没する事件が発生します。
この時すでに隠居の身だった松前道広は息子の章広や家臣たちの反対を押し切って、自ら出陣しようとしたと言われています。道広は自身を「北方の守護者」と認識していたようです。
道広は強気な性格で蝦夷地防衛への強い執着心があったようです。彼の行動は、まさに「遅れてきたもののふ」と呼ぶにふさわしいものでしたね。
14年間にわたる謹慎の真相とは?
文化4年(1807年)3月。松前道広は突如、幕府から謹慎を命じられました。
その理由は、藩主時代の海防への取り組みにおける問題点や、度重なる彼の素行の悪さが挙げられています。
元家臣による讒言(ざんげん)があったとも言われていますが、この謹慎は14年間にも及びました。彼は長い間、謹慎生活を強いられ文政5年(1821年)3月になってようやく謹慎が解かれることになります。
79年の生涯を閉じる!松前道広の最期と後世への影響
天保3年(1832年)6月20日。松前道広は江戸で79年の生涯を終えました。彼は蝦夷地という特殊な地域で藩主としての重責を担いながら、破天荒な行動で常に周囲を驚かせました。
蝦夷地の歴史に残した足跡とは?
松前道広の治世は松前藩の蝦夷地支配体制に大きな影響を与えました。彼が行った北方への強硬な対応や、アイヌの反乱鎮圧は、幕府の蝦夷地に対する認識を深めるきっかけとなります。
結果として後の蝦夷地直轄化へと繋がっていく重要な流れを作り出したのです。
大河ドラマ「べらぼう」の松前道広!史実との違い
えなりかずきが大河ドラマ出演
2025年放送のNHK大河ドラマ「べらぼう」では、浮世絵師の蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)の生涯が描かれます。このドラマで松前道広を演じるのは、俳優のえなりかずきさんです。
一時期芸能界から干されていましたと言われますけど、こうしてテレビ画面に戻ってきたのは嬉しい限り。今までの鬱憤をはらすかのような、弾けた演技を見せてくれます。むしろこういう陰のある役もできるようになって、芸の幅が広がったのでは?と思います。
えなりかずきさんが演じる「北辺に巣くう鬼」とは?
ドラマでは松前道広は武芸に優れ「遅れてきたもののふ」と評される一方で、残虐な一面も持つ人物として描かれます。
例えば宴会の余興で粗相をした家臣の妻を木に括りつけ、その近くに的を設置し火縄銃で撃つといった行為が描かれました。とんでもない暴君ですね。これは彼が家中を恐怖で支配していた様子を表していますね。
また、劇中の湊(みなと)という人物の証言では、松前道広は蝦夷の民にひどい仕打ちをするばかりか、ロシアとの抜荷(ぬけに、密貿易のことですね)も行っていたとされています。そのため、湊からは「北辺に巣くう鬼」とまで言われているのです。
史実とドラマ描写を比較してみると?
大河ドラマ「べらぼう」では、松前道広の残虐な面が強く強調されています。史実では彼の「傲慢な性格」や「素行の悪さ」は伝えられていますが、ドラマではそれをさらに過激な形で表現しています。
ドラマはエンタメ作品ですから、人物の善悪をはっきりさせたり、人物のコントラストを極端に描くのが当たり前です。特にドラマでは主人公(蔦屋・田沼サイド)の敵対勢力にいる人物なので、極端な悪人に描かれやすいのですね。
あとがき
松前道広は若くして蝦夷地の松前藩の藩主となり、北方からの脅威に毅然と立ち向かう一方で、その派手な私生活や反骨精神は時に藩財政を逼迫させ、幕府からの謹慎処分へと繋がりました。
蝦夷地の防衛に並々ならぬ情熱を注ぎ「北の守護者」としての強い自覚を持っていた彼は、単なる浪費家や傲慢な人物として片付けられない一面もあったと言えるでしょう。
2025年の大河ドラマ「べらぼう」では、えなりかずきさんが演じる松前道広は個性的な側面をさらに強調。暴君的な「北辺に巣くう鬼」として描かれています。
エンターテイメント作品としての脚色が加えられているため、史実とは異なる残虐な描写もありますが、これはドラマがエンタメ作品として作られているためです。
ドラマをきっかけに松前道広に興味を持った方は、ぜひ史実と見比べてみてはいかがでしょうか?そうするとより一層、彼の生涯が興味深いものに思えるはずです。


コメント