NHKドラマ『ばけばけ』に登場するレフカダ・ヘブン。左目が見えないという設定には、実在のモデルである小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の人生が深く関わっています。
16歳で左目を失明したハーンは、その喪失を通して“見えない世界”への感性を育てました。この記事では、史実とドラマの演出を比較。彼の「片目」が象徴する意味を考察します
この記事でわかること
- 小泉八雲が左目を失明した経緯とその影響
- 『ばけばけ』での片目の演出意図と俳優の表現
- 片目が象徴する「現実と異界」「見えるものと見えないもの」の関係
小泉八雲は16歳で左目を失明していた

レフカダ・ヘブンのイメージ
レフカダ・ヘブンのモデルは、明治期に日本で暮らした作家小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)です。
三才ブックス刊『小泉セツ』によると、
「16歳のとき、校庭で遊んでいたところ事故にあい、左目を負傷。
手術をするも治らず失明してしまう。
ハーンの肖像に左目を隠した写真が多いのはこのため。」
また別の記録では、寄宿学校での事故による怪我だったとも伝えられています。
いずれにしても、彼は16歳のときに片目の視力を失いました。その後は生涯にわたって片目のまま生きることになります。
この出来事はハーンの人生観を根底から変えたのではないでしょうか?後に彼は音を感じ取る感性に敏感になり、見えないものを見たい・知りたいと思う気持ちに繋がるような気がします。
代表作『怪談』や『知られざる日本の面影』に描かれる“不可視の世界”や“人の心の奥”――
それらはまさに、あの事故によって生まれた**“もう一つの視点”、
すなわち失われた左目が見つめる世界**から生まれたものなのです。
左目を失明している役
『NHKテレビドラマガイド ばけばけ』(p.15–16)によると、
レフカダ・ヘブンは「左目を失明している役」として設定されています。
俳優のトミー・バストゥさんは次のように語っています。
「視界が悪くなるのでコンタクトは着けなくてもいいと言われたのですが、
作品にとって重要なのは、私が大変かどうかではありません。
ヘブンの左目を見て、他の人がヘブンにどうリアクションするかが大切なんです。」出典:『NHKテレビドラマガイド ばけばけ』(p.15–16)
トミーさんは撮影で白濁した特殊コンタクトレンズを装着し、視界の制限をリアルに体感することで、孤独や異質さを自然に表現しています。
さらに、ハーン本人がそうであったように、猫背の姿勢や下から見上げるような視線を意識して演じており、その眼差しの演出が、人物の存在感に深みを与えています。
一見すると幻想的な白い左目ですが、それは単なる造形ではなく、他者との距離感や、異文化との向き合い方を象徴する演出と言えると思います。
レフカダ・ヘブン:#トミー・バストウ
新聞記者として取材のために来日したが、縁あって松江で英語を教えることになる。
同僚の英語教師・錦織友一のサポートを受けながら、松江での日々を送る。ひょんなことから、トキと出会い交流が始まる。#ばけばけ #9月29日スタート pic.twitter.com/zfPnNW0tYJ— 朝ドラ「ばけばけ」公式|9月29日(月)放送開始 (@asadora_bk_nhk) August 4, 2025
視線の演出が映す、ヘブンの“孤独の記憶”
トミー・バストゥさんが語った
「ヘブンの左目を見て、他の人がどうリアクションするかが大切なんです」という言葉。
このコメントには、彼という人物の過去の痛みや孤立をリアルに描こうとする意図が込められていると思います。
ヘブンやモデルとなった小泉八雲は幼いころから“異質な存在”として扱われてきました。
母はギリシャ人、父はアイルランド人。複雑な出自に加え、さらには両親との離別・叔母の破産による貧困。左目の失明という外見上の特徴を負ったことで、周囲の偏見や好奇の目にさらされることも少なくなかったといいます。
そんな経験が彼を内向的で気難しい性格へと導いたのかもしれません。人と距離を置いているのに、心の奥では「理解されたい」と思う気持ち。そんな複雑な心を、“ヘブンの左目”という形で表現しているのかもしれません。
視聴者がヘブンの白濁した左目を見て思うのは、たぶん小泉八雲が受けた周囲の反応そのもの。この視線の演出は「彼がどう見られてきたか」という社会的な記憶の再現でもあるのです。
片目の演出から読み取る『ばけばけ』のテーマ
レフカダ・ヘブンの“片目”という設定は、もちろん実在の小泉八雲がそうだったからなのですが。片目が白濁した演出をしない選択もあったそうです。でもあえて目が見えないことがはっきりと分かる演出になったそうです。
これはドラマの演出にもうまく合っていると思います。『ばけばけ』のテーマは、「この世は恨めしい、だけどすばらしい」。白濁した片目はこの相反する二つの世界を象徴するモチーフといえるのではないでしょうか?
見えるものと、見えないもの。
現実と、異界。
彼はその間に立ち、どちらの世界も見つめようとしている。
失明という痛みを背負いながらも、彼は“もう一方の世界”を心の眼で見ようとする人として描かれています。
ドラマ的な解釈だと、見えない左目は「心で見ること」そのものの象徴。と言えるかもしれません。
『ばけばけ』という作品が描く“生と死”“この世とあの世”の境界線を、
彼の片目が静かに見つめていると解釈できるのです。
「片目」が象徴するもの= 見える世界と見えない世界
「見えないもの」へのまなざし
小泉八雲は、目に見えないもの、つまり幽霊や妖精、精霊といった存在に強い興味を持っていました。
大人になってからは、各地で語り継がれてきた不思議な話を集め、『怪談』などの作品として出版しています。
“見えないものへの憧れ”は、ギリシャやアイルランドといった彼のルーツにも関係しているのかもしれません。
どちらの土地にも、自然の中に神秘や霊が宿るという古い信仰が息づいています。
けれど、その興味の根っこには、彼自身の片目を失った経験もあったのではないでしょうか。
心の目で見えるものを求めて
世界の半分を失ったことで、彼は目に映らないもう半分。心の目でしか見えない世界に、より深く惹かれていったのかもしれません。
『ばけばけ』という作品全体の中で、レフカダ・ヘブンの“左目”は「見えない世界を感じ取る感性」そのものを象徴しているといえます。
-
異文化の境界に立つ存在
半分は“見える”、半分は“見えない”。
異国で生きる彼の孤独や戸惑いを象徴。 -
内面世界への洞察
見えない左目が他者の心や“異界”を感じ取る力に変わる。 -
“片目”=偏りと共感のあいだ
不完全な視覚だからこそ、人間らしい誠実さが際立つ。
彼のまなざしは地上と天を結ぶ人という名前の意味にも通じています。「レフカダ(地名≒地上)」と「ヘブン(天)」の名が意味するように。現実と理想、見えるものと見えないものの間で生きる象徴的存在なのかもしれません。
まとめ:左目は“異界と現実をつなぐ視線”
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 史実 | 16歳で左目を負傷・失明 |
| ドラマ演出 | 白濁コンタクトで再現、姿勢・視線まで史実に忠実 |
| 象徴的な意味 | “片目”=見える世界と見えない世界をつなぐ視点 |
レフカダ・ヘブンの左目はハーンが実際に負った痛み。見えないものを見ようとする人間のまなざしを象徴しているといえるのではないでしょうか。
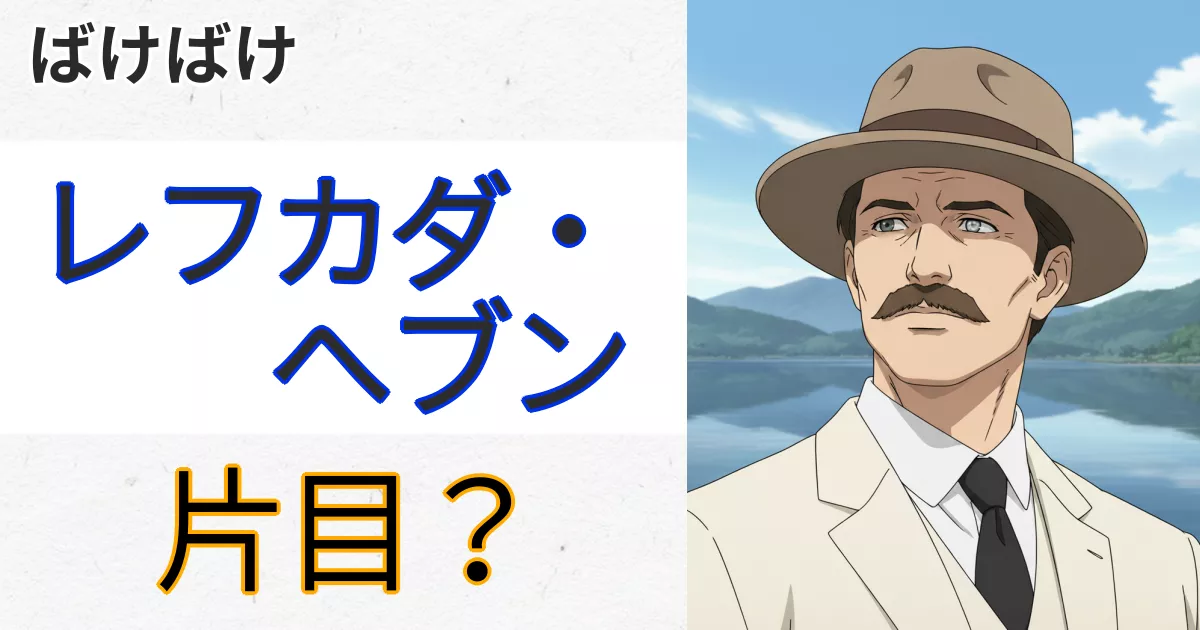
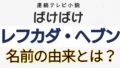
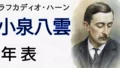
コメント