レフカダ・ヘブンは、NHK朝ドラ『ばけばけ』に登場する外国人教師。明治期の作家 ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)がモデル。“レフカダ”は八雲の出生地名に由来するという説があります。
この記事ではヘブン役の人物像とモデルとなった小泉八雲の生涯や著作、逸話までを詳しく紹介、ドラマ視聴をより楽しむための情報をまとめました。
この記事でわかること
・レフカダ・ヘブンの人物像と名前の意味
・モデルとなった小泉八雲の生涯と共通点
・ドラマ『ばけばけ』における史実との違い
レフカダヘブンとは?
レフカダ・ヘブンは、NHKの朝ドラ『ばけばけ』に登場する外国人教師です。
モデルになっているのは、明治時代の作家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)です。
物語の舞台は松江。
レフカダ・ヘブンは、NHKの朝ドラ『ばけばけ』に登場する外国人教師です。
モデルになっているのは明治時代の作家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。実在の人物をもとにした、少し風変わりでミステリアスなキャラクターです。
物語の舞台は松江
ヘブンはもともと新聞社の依頼で日本旅行記を書くために来日します。取材のつもりでやってきた彼でしたが、英語教師として招かれてしまうんですね。
そこから始まるのが異文化の中での戸惑いと発見の物語です。
最初は文化の違いに困惑し、なかなか周囲と打ち解けられません。気難しく見えたり、変わり者だと思われたりもします。それでも日本人との交流を通して少しずつ心を通わせていく。そんなヘブンの姿が描かれます。
日本文化や怪談など“日本的なもの”に惹かれながらも、完全には馴染めない孤独。その中で見つける小さな優しさや理解の瞬間が、物語の大きなテーマになっています。
どこか不器用で、でも真っすぐに日本を愛する彼の姿が印象的です。
モデルは小泉八雲。どこが重なる?
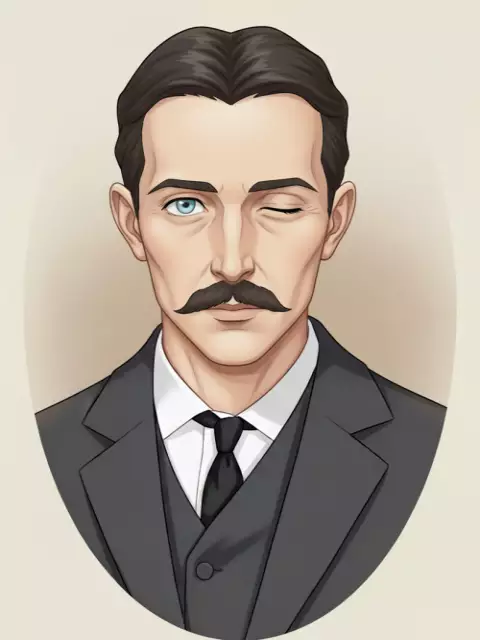
ラフカディオ・ハーンのイメージ
レフカダ・ヘブンは、明治時代に松江で暮らした作家 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) をモデルに設定したキャラクターです。
ただし、ドラマ『ばけばけ』は八雲の人生をそのまま再現するのではなく、史実をもとに人物像や人間関係を再構成しています。
共通点①:新聞記者として来日 → 松江で英語教師に
史実の八雲は1890年、アメリカの新聞社の特派員として来日しました。この点はドラマでも忠実に再現されています。
彼は来日後すぐに契約を打ち切り日本に残ることを決意。その後、島根県の師範学校と尋常中学校で英語教師となり、松江での生活を始めます。
ドラマのヘブンも同様に新聞記者として来日。その後、島根初の外国人教師として迎えられる設定です。
取材目的から教育の道に進むという転換は一致しています。
共通点②:通訳の存在と“言葉の壁”
史実でも八雲が松江に赴任した当初は日本語をほとんど理解できず、通訳を務めたのが西田千太郎(錦織友一のモデル)でした。
セツがハーンの言葉を理解できるようになるのは、彼女と出会ってからしばらく経ってからのことです。
この点をドラマでは錦織友一がヘブンの通訳を担当する形で再現。この設定は完全な創作ではなく、史実の初期段階を踏まえた描写です。
共通点③:日本文化への関心
八雲は来日後、日本の暮らし・風習・信仰に深い興味を抱きました。
ドラマのヘブンも、着物・扇子・障子・侍など、目に映る日本の生活文化に惹かれる描写があります。
ただしこの段階では史実のような「怪談収集」や「文学的探究」はまだ描かれていません。
文化を“観察する外国人”という立場に留まっており、そこが後年の八雲(=文学者)と異なる最大のポイントです。
共通点④:松江の風景と空気感
史実でも八雲が最も心を寄せた場所が松江でした。宍道湖の水面、和の暮らし、静かな町並み。ドラマでもこの情景を忠実に再現し「異国で心を落ち着けていく青年」という様子を描くようです。舞台の情緒そのものが、史実の八雲を象徴する要素となるのでしょうね。
違い①:教師としての立場と心理描写
史実の八雲は、教育者としての職務意識が強く松江の生徒たちからも「情熱的な教師」として慕われていました。
一方、ドラマのヘブンは少なくとも最初の段階では“代用教員としての不安”を抱く青年として描かれています。「自分は専門家ではない」という劣等感を持ち、逃げ豊島場面もあります。
でも彼なりに懸命に生徒や同僚と向き合う姿が、朝ドラらしい人間ドラマとして脚色されています。
レフカダ・ヘブンが片目のわけ

レフカダ・ヘブンのイメージ
レフカダ・ヘブンは“片目が見えない”設定です。これはモデルになった小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の実体験がもとになっています。
ハーンは16歳のとき、学校での事故が原因で左目を失明しました。この出来事が彼の感性を大きく変え、「見えない世界」への洞察力を育てたといわれます。
ドラマでは俳優トミー・バストゥが、白濁した特殊レンズを使ってヘブンの孤独や異質さを表現しています。
ヘブンの左目は、他者との距離、そして“見られる痛み”を象徴するモチーフとして描かれているのではないでしょうか。また見える右目と見えない左目に秘められた演出の糸もあるかもしれません。
詳しくは、レフカダヘブンの左目に秘められた意味|片目で見るもう一つの世界を御覧ください。
名前の由来は?「レフカダ/ヘブン」の意味
朝ドラ『ばけばけ』の外国人教師・レフカダ・ヘブンという名には、モデルとなった小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の出自と名の由来が深く関係しています。
「レフカダ」は彼の生まれたギリシャの島の名で、ミドルネーム “Lafcadio” にも通じる“ルーツを示す言葉”。
一方「ヘブン(Heven)」は、ハーンの姓 “Hearn(ヘルン)” の響きと “Heaven(天・心の居場所)” の象徴を重ねたものと考えられます。
つまりこの名は、“異国で心の居場所を見つける青年”という物語そのものを表しているのです。
さらに詳しくは レフカダ・ヘブンの名前の由来は? で解説していますので御覧ください。
演じる俳優は誰?
トミー・バストウとは
レフカダ・ヘブン:#トミー・バストウ
新聞記者として取材のために来日したが、縁あって松江で英語を教えることになる。
同僚の英語教師・錦織友一のサポートを受けながら、松江での日々を送る。ひょんなことから、トキと出会い交流が始まる。#ばけばけ #9月29日スタート pic.twitter.com/zfPnNW0tYJ— 朝ドラ「ばけばけ」公式|9月29日(月)放送開始 (@asadora_bk_nhk) August 4, 2025
レフカダ・ヘブンを演じるのは、イギリス出身の俳優トミー・バストウ(Tommy Bastow)。
1991年8月26日生まれ。映画『ジョージアの日記/ゆーうつでキラキラな毎日』(2008)で俳優デビューし、英国ドラマ『The Crossing』や日独合作『ザ・ウィンドウ』(2022)など国際的に活躍してきました。
2024年には海外ドラマ『SHOGUN 将軍』でマルティン・アルヴィト司祭を演じ、その存在感が高く評価されています。
NHK朝ドラ『ばけばけ』では1767人の応募者の中から選ばれた唯一の外国人主要キャスト。
本人は10年以上日本語を学んでおり、取材では「言葉よりも感情で通じ合う演技を目指したい」と語っています。
英語・日本語の双方で繊細な演技ができる俳優として、今作が日本での本格的な代表作となります。
ドラマと史実の違い
▼レフカダ・ヘブンと小泉八雲の比較
| 項目 | ドラマ「ヘブン」描写 | 史実「八雲」 |
| 出身・背景 | ギリシャ出身。幼少期に両親と離別し、孤独な少年期を過ごす。 | ギリシャ・レフカダ島生まれ。父はアイルランド人、母はギリシャ人。幼少期に両親が離婚し、伯母に育てられる。 |
| 来日・職業 | 新聞記者として来日。のちに島根初の外国人教師として歓迎されるが、自身は“本職の教師ではない”ことに不安を抱く。 | 1890年、米国新聞社の特派員として来日。その後、松江尋常中学校・師範学校で英語教師を務めた。 |
| 名称・名前 | 「レフカダ・ヘブン」という創作名。 | 本名は Lafcadio Hearn/日本名:小泉八雲(Koizumi Yakumo)。 |
| 日本語能力・交流 | 日本語を話せず、通訳は同僚の錦織友一が担当。言葉が通じない中で、表情や仕草で交流する。 | 来日当初は日本語が不自由で、妻セツが通訳を務めた。後年は「ヘルンさん言葉」と呼ばれる片言を話す。 |
| 関心の対象 | 着物・扇子・障子・侍など、日本の生活文化や風習に強い興味を示す。初期段階では怪談への関心は描かれていない。 |
八雲は来日後、日本の民話や怪談、古典文学に魅了され、『怪談』『知られざる日本の面影』を著した。 |
まとめると:
ドラマ『ばけばけ』は小泉八雲の人生を忠実に再現したドラマでは有りません。彼の人生をもとに朝ドラ向けに脚色された人物です。
異文化を理解しようとする誠実さ、人々との絆、そして物語をして日本文化を愛した精神。これらを受け継ぐ形で、レフカダ・ヘブンという人物が描かれています。
関連記事
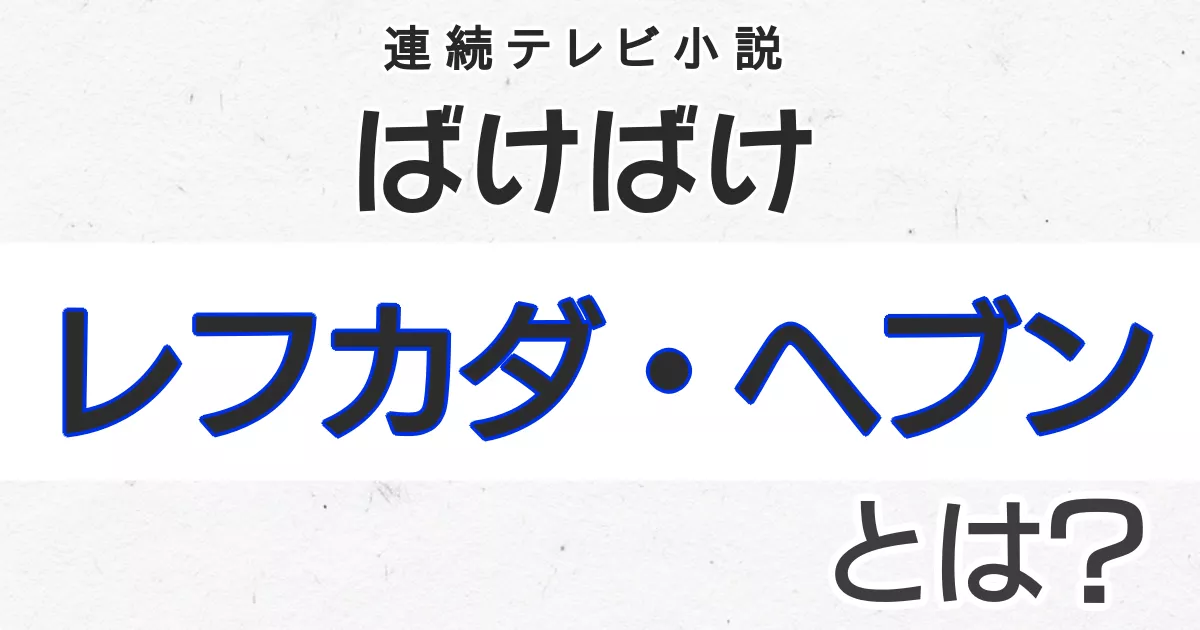
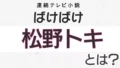
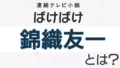
コメント