一橋治済(ひとつばし はるさだ)は11代将軍・徳川家斉の父親です。
一橋家当主として幕政に深く関わり、田沼意次を排して松平定信を登用するなど、激動の時代を生き抜きました。
息子を将軍にさせ権勢をふるった一方で、その生涯は常に権力争いと対立に彩られていました。
今回はそんな一橋治済の波乱に満ちた生涯をその生い立ちから晩年まで詳しく見ていきましょう。
一橋治済
没年:文政10年2月20日(1827年3月17日)
名前:徳川 治済(とくがわ はるさだ)
別名:一橋 治済
幼名:豊之助
家系:一橋徳川家
家族
母親:由加
子供: 家斉、治国など。
一橋治済の生い立ちと兄弟の関係
一橋治済は徳川幕府八代将軍・徳川吉宗の四男 徳川宗尹の四男として生まれました。つまり、吉宗の孫です。
治済には、兄が2人いました。
- 長兄:松平重昌:越前国福井藩の藩主となりました。
- 三兄:松平重富:同じく越前国福井藩の藩主となりました。
つまり、治済の兄2人は、すでに大きなお殿様になっていたのです。
一橋家の後継者へ
治済の兄たちが藩主として家を出た後、治済がまだ幼い頃に、一橋家の後継者となりました。これは、将来、将軍になる可能性を秘めた重要な役目です。
その後、元服(成人式)を迎え、正式に一橋家の家督を継ぎました。
明和4年(1767年)には公仁親王の娘・在子女王と結婚。
天明元年(1781年)には参議(納言の下)になりました。
息子を次期将軍にする
安永8年(1779年)。第10代将軍・徳川家治の世嗣・徳川家基が急死。家治には他に息子がいないため後継者問題が起こりました。
そこで田沼意次と連携して息子の家斉を次期将軍候補にするため働きかけましtあ。
一橋家は意次の弟・意誠やその子・意致が家老になっていました。そのため田沼家とは縁が深いのです。
その結果。息子の家斉が将軍徳川家治の養子になりました。
田沼意次に反発
一橋家と田沼家は縁が深いです。でも治済は田沼意次の政治はあまり快く思っていなかったようです。
10代将軍 家治の時代。田沼意次が強力な権力を握り幕府財政の立て直しを図るため重商主義を推し進めました。
しかしその一方で拝金主義的な傾向が強まり、汚職が蔓延。旧来の価値観を破壊しているように見える田沼意次のやり方には批判も強かったのです。
特に親藩、譜代の大名からは成り上がり者の田沼意次の権勢を警戒する声も上がっていました。
一橋家当主の治済は田沼派の政治に不満を抱き次第に反発するようになります。
治済と松平定信:反田沼派の連携
10代将軍 徳川家治が亡くなり11代将軍・家斉が就任すると田沼意次が老中を解任。家斉が若いため一橋治済と御三家が家斉をサポートする形で家斉の治世が始まります。
もともと田沼政治に不満を持っていた治済と御三家は残る田沼派を排除。御三家が推薦する白河藩主 松平定信を老中に迎えることに同意しました。
松平定信は学識豊かな人物で、田沼派の政策を批判、改革を訴えていました。
しかし田沼派の抵抗にあってなかなか進みません。そこに天明の打ちこわしが起こり、対応のまずさから責任を取らされ田沼派が次々失脚。
治済と御三家は残る田沼派を一掃して松平定信を老中にすることに成功しました。
田沼派の失脚と幕政の転換
これにより幕政は大きな転換期を迎えます。定信は寛政の改革と呼ばれる一連の改革を行いました。
一橋治済と松平定信の対立:大御所問題
しかし一橋治済と松平定信の協力関係は長くは続きません。
田安家出身で一時は将軍候補とも言われた松平定信でしたが。白河藩主の要請に応えて、定信を白川藩に追いやるために協力したのは田沼意次と一橋治済でした。
しかも松平定信の厳しすぎる改革に不満が続出。
天明8年(1788年)。11代将軍 徳川家斉が父 一橋治済に「大御所」の尊号を贈ろうとしたことから老中・松平定信の対立は決定的となりました。
大御所問題の背景
- 大御所とは: 本来は隠居した将軍に与えられる尊称。実質的な権力を持つ存在でした。
- 治済の意図: 家斉は実父の治済に大御所の称号を与え親孝行をするとともに。治済の政治的な影響力を高め自身の権力基盤を強化しようと考えました。
- 定信の反対: しかし老中・松平定信が将軍・家斉の意向に真っ向から反対しました。
なぜ松平定信は治済の大御所に反対したのか?
- 前例がない:将軍職を経験したことのない者が大御所になった前例がない。
- 朝廷への配慮:当時、朝廷では光格天皇が実父・典仁親王に太上天皇の尊号を贈ろうとしていました。定信はこれに反対しています。典仁親王の太上天皇に反対している以上、似た立場にある治済の大御所を認めるわけにはいきません。
- 治済への不信感:もともと治済は定信を白河藩の養子に追いやった者のひとり。定信は治済に不信感を持っています。
- 治済が権力を持つことへの反発:治済が大御所待遇になれば今以上に治済の発言力が増します。
徳川家斉は定信の説得と反対にあってしぶしぶ父を大御所にするのを諦めました。
しかし怒りの収まらない家斉と治済は定信を解任します。
一般には寛政の改革への不評から解任されたと言われますが。定信が去った後も寛政の改革は続けられているので、寛政の改革の不評よりも大御所問題の方が定信にとっては致命傷になったのです。
一橋治済の晩年と死後
その後、一橋治済は晩年まで幕府や朝廷で重要な地位を歴任し、大きな影響力を持っていました。
- 官位の上昇: 寛政3年には権中納言、寛政11年には従二位権大納言に昇進しました。
- 隠居と栄誉: 寛政11年に家督を譲り隠居した後も幕府から多額の収入を得て、高い地位を保っていました。剃髪して穆翁と名乗り、朝廷から特別な許可を得て裘袋を着用するなど、晩年は宗教的な活動にも力を入れていたようです。
- さらなる昇進: 死後も内大臣や太政大臣といった臣下の最高位を追贈されました。
文政10年(1827年)2月20日。一橋治済が死去。77歳の生涯を閉じました。
まとめ
一橋治済は徳川吉宗の孫で一橋家の当主となりました。
徳川家治に跡継ぎがいなくなったことから、田沼意次と協力して息子の家斉を11代将軍にしました。しかし家治の死後は田沼意次を排除して松平定信を老中に迎え入れます。
しかし徳川治済に大御所の尊号を与えることに松平定信が反対したので定信を失脚させました。
治済は自身や息子の地位向上や繁栄のために幕政に深く関わり激しい権力闘争を繰り広げました。その一方で晩年は宗教に傾倒し、文化的な面もみせました。
治済の生涯は、敵味方が激しく入れ替わる江戸幕府の政治・権力闘争がどれほど複雑で激しいものだったかを現す一例と言えますね。
テレビドラマ
八代将軍吉宗 1995年、NHK大河ドラマ 演:広瀬斗史輝→嶋田伸亨→徳山秀典→山下規介
陽炎の辻 完結編 2017年、NHK正月時代劇 演:山本學
大奥 2023年、NHK総合ドラマ10 演:松風理咲
大奥 2024年、フジテレビ 木曜劇場 演:陣内孝則
新暴れん坊将軍 テレビ朝日、2025年 演:駒木根葵汰
べらぼう 2025年、NHK大河ドラマ 演:生田斗真
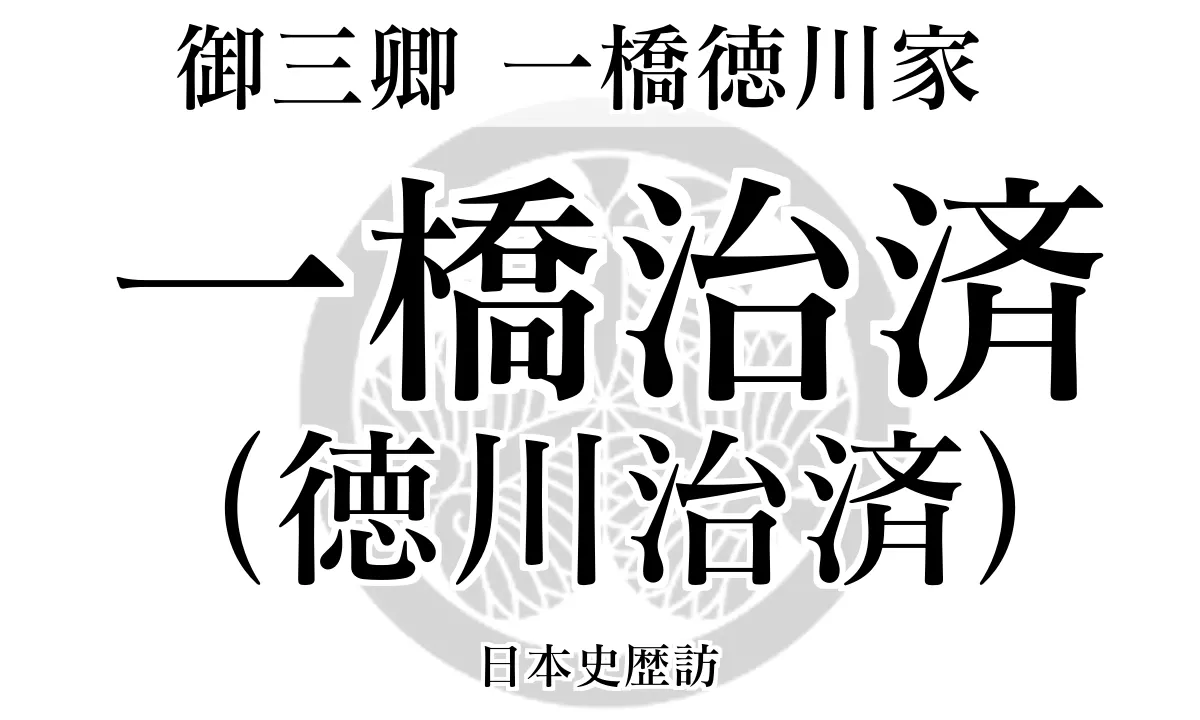
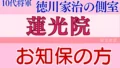
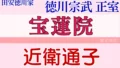
コメント