宝蓮院(ほうれんいん) 近衛通子は田安徳川家初代当主・徳川宗武の正室。
摂関家の近衛家の出身。徳川吉宗の三男・徳川宗武と結婚しました。
治察ほか7人の子を生みましたが半数以上が幼くして亡くなっています。宗武の側室が産んだ賢丸(松平定信)も育てました。
宗武の死後は落飾して宝蓮院と名乗りました。
息子の治察が田安家を継いだものの若くして病死。田安家を守るため努力しますが田安家はしばらく跡継ぎがいない状態になってしまいます。
この記事では史実の宝蓮院を解説。大河ドラマ『べらぼう』に登場する宝蓮院についても紹介します。
- 宝蓮院の生涯: 摂関家出身、徳川宗武の妻、子供たちの教育、晩年の落飾など、波瀾万丈な人生を送った。
- 家族: 夫の徳川宗武、子供たちの数々の死、養子に出された松平定信など、家族関係に多くのドラマがあった。
- 田安家の後継問題: 松平定信を後継者にしたいという願い、幕府の反対、田安家が明屋敷になった経緯など。
- ドラマ『べらぼう』における宝蓮院: 花總まりさん演じるドラマでのキャラクター像、史実との関連性など。
宝蓮院とはどんな人?
生誕: 元文2年11月15日(1737年12月6日)
没年: 寛政3年3月8日(1791年4月10日)
家族
子供:
誠姫・裕姫(夭折)・小次郎(夭折)・銕之助(英菊)(夭折) ・仲姫・徳川治察(田安徳川家2代)・節姫
宝蓮院のおいたち
蓮光院は8代吉宗の時代・享保6年(1721年) に生まれました。
宝蓮院が生まれた近衛家は摂関家の一つ。近衛家は5つある摂関家でも一番格式の高い家です。
父の近衛家久は太政大臣として公家のトップに立つ人物でした。
近衛家久は公家の頂点として朝廷の政を仕切るだけでなく、文人としても才能を発揮しました。特に茶道や有職故実(朝廷の儀式や服装に関する学問)に造詣が深く、数多くの和歌を残しています。彼の日記『家久公記』は当時の宮廷文化や社会情勢を知る上で貴重な史料となっています。
そんな家で育った蓮光院も幼少の頃から和歌や書道などの教養をしっかりと身につけ、名門の娘にふさわしい女性に育ちました。
吉宗が息子の妻にと望んだのも当然かも知れません。
13歳で徳川宗武と結婚
享保18年(1733年)。13歳の若さで江戸城二の丸に入り。
享保20年(1735年)。徳川宗武と結婚します。
宝蓮院は公家の名門の娘から一転して武家の頂点・徳川家という重責を担う家の当主の妻となり新しい人生を歩み始めることになります。
夫になった徳川宗武とは
宗武は8代将軍 徳川吉宗の次男。このころの徳川宗武は将軍の息子として江戸城で暮らし、周囲の重臣からも次期将軍候補として期待がかけられていたころでした。
しかし吉宗は長男・家重に家督を注がせることを決めていました。宗武は御三卿の一つである田安徳川家の初代当主になります。
宝蓮院も御三卿の正妻となりました。
子どもたち
宝蓮院と宗武の間には誠姫、裕姫、小次郎、銕之助、仲姫、徳川治察、節姫の7人の子供が生まれました。
でも裕姫、小次郎、銕之助が幼くして亡くなり、誠姫も結婚前に亡くなってしまいます。宝蓮院は大きなショックを受けたことでしょう。
また治察は一橋家を継ぎましたが病弱でした。
松平定信の養母
徳川宗武の七男の賢丸(松平定信)は宝蓮院の子ではなく側室の子です。でも賢丸は宝蓮院が育てました。
治察が病弱で跡継ぎを残せなかったため、賢丸にも田安家後継ぎの期待がかかっていました。
宝蓮院はこれらの子供たちを厳しくも愛情深く育て上げました。
賢丸が白河藩の養子に出されてしまう
ところが白河藩藩主・松平定邦が賢丸を養子にしたいと希望。田安家は断りましたが、松平定邦は田沼意次に働きかけ白河藩へ養子が決まってしまいます。
宝蓮院としては愛情をもって育て将来を期待していた賢丸を奪われ憤ったに違いありません。
晩年と死
明和8年(1771年)。夫の宗武が死亡。その後、宝蓮院は落飾。宝蓮院と名乗りました。
その後も田安徳川家の家督を継いだ息子・治察を支え家を守り続けました。
しかし治察も 安永3年(1774年)に死亡。田安家は断絶の危機に陥ってしまいます。
松平定信を後継者に望むものの
このとき田安家には松平定信がいました。定信は、陸奥国白河藩主・松平定邦の養子となっていましたが、まだ田安家に住んでいました。
そのため、宝蓮院は定信が田安家を継ぐことを望み、大奥の老女 高岳に定信を田安家の跡継ぎにしたいと伝えました。
ところが幕府の意向により、定信の相続は認められませんでした。
徳川家治の側衆 稲葉正明が吉宗の意向として「御三卿の当主に子供がいない場合は相続は認められない」と言われてしまいます。
結局、田安家は後継ぎがいないまま「明屋敷」となって年月が過ぎてしまいます。
御三卿は「将軍の身内・将軍後継者の供給源・および将軍の血筋を残すための家」という特殊な位置づけのため、当主がいなくなっても断絶とはならず。領地や家臣はそのまま残され幕府が管理します。この状態を「明屋敷」といいます。
天明6年(1786年)。66歳で生涯を閉じ寛永寺凌雲院に葬られました。
その後の田安家
宝蓮院の死の翌年。天明7年(1787年)松平定信が老中になりました。
松平定信は一橋治済の五男 斉匡に田安家を継ぐよう命令。このとき御三家から反対がありました。というのも「御三卿は将軍庶子の受け入れ先」として作られたというのです。
でも定信は養母 宝蓮院の願いだとして説得しました。
田安家は14年ぶりに当主を迎えることができました。定信としては思い入れのある田安家を残したい・養母の願いを叶えたいという気持ちがあったのでしょう。しかしその頃にはすでに宝蓮院がこの世にいなかったのは残念です。
大河ドラマ「べらぼう」の宝蓮院
2025年 大河ドラマ『べらぼう』では宝蓮院は花總まりさんが演じます。単なる武家の妻という枠を超えた魅力的な女性として描かれています。
田安徳川家・徳川宗武の正室としての立場
宝蓮院は史実通り御三卿の一つである田安徳川家の初代当主・徳川宗武の正室。
実の子の治察以外にも側室の子・賢丸と種姫も育てました。
ドラマに登場するのは宝蓮院として登場するのは夫の徳川宗武が亡くなった後。
でも後を継いだ息子の治察は病弱で跡継ぎを残せない。賢丸も白河家に養子として出されようとしています。
宝蓮院は賢丸を失うのは避けたいと思っていますが。どうやら止められない様子。
宝蓮院は名門の妻としてその役割を全うするために、様々な困難を乗り越えていきます。
名門の娘としてのプライド
宝蓮院は摂関家の一つである近衛家の娘として生まれました。近衛家は5つある摂関家のひとつ。
その近衛家で生まれ育ち、将軍・徳川家治の三男と結婚。御三卿・田安家の投手の妻となりました。生まれも育ちも当時の武家社会ではトップクラスの名門です。
ドラマにおける宝蓮院の役割と史実との関連
ドラマ『べらぼう』では宝蓮院は、生まれ育った背景から非常に気位が高い人物として設定されているようです。
足軽からのし上がった田沼意次を見下しています。でも策略家の田沼意次にはことごとくしてやられるという役回りのよう。
宗武の娘・種姫といえば史実では十代将軍・家治の養女になりました。次期将軍として期待のかかる家基の正室にするためと言われています。
ドラマでもこの説が採用される可能性は高いですね。その場合も宝蓮院が動いて種姫を将軍の幼女にするのでしょうね。
治察は若くして無くなることが予想されますが、田安家を守るために賢丸とともに奮闘する姿が描かれるのでしょう。
ドラマの宝蓮院はプライドが高いけれどもただのお嬢様ではない。様々な手段を使って田安家を守り抜こうと奮闘する女性のようです。
花總まりさんがどのように演じるのか楽しみです。
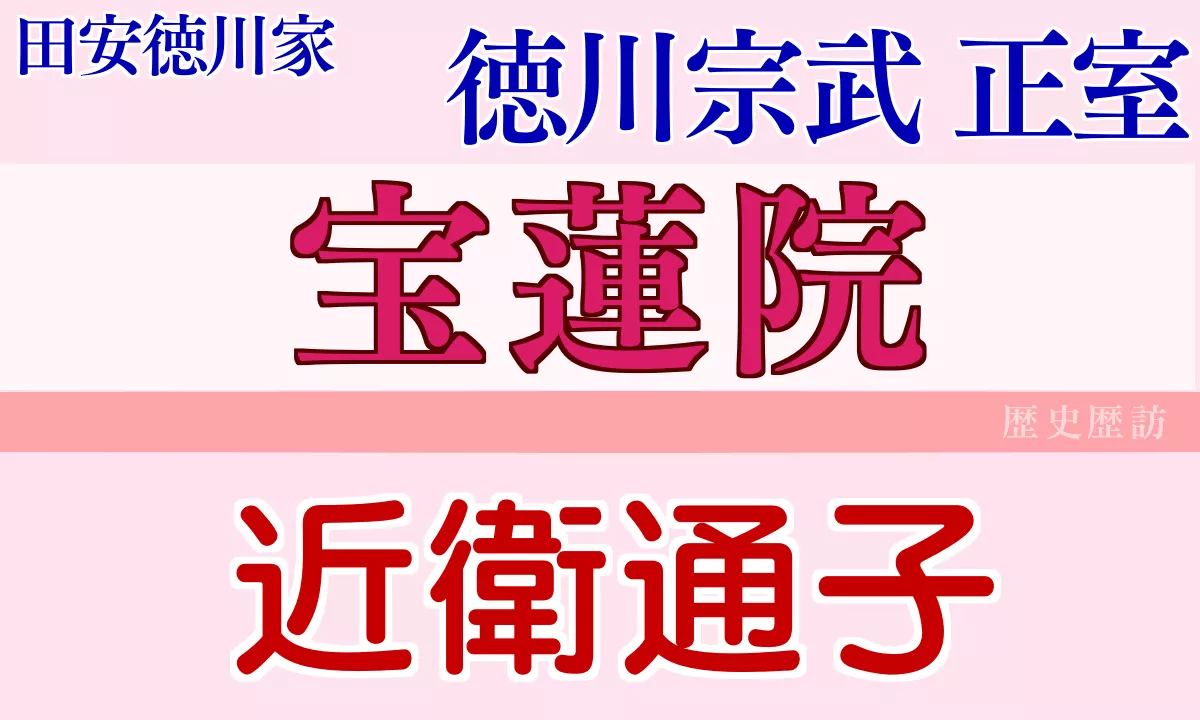

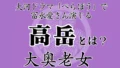
コメント