小泉セツ(節子)(1868年~1932年)は、文豪ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の妻であり、彼の日本における著作活動を陰で支えた女性です。幼少期から民話や伝承を好み、家計を助けるために織子として働いた苦労人でもありました。
近年では、朝ドラ「ばけばけ」で小泉セツをモデルにしたヒロイン・松野トキが登場し、彼女の生涯や功績に再び注目が集まっています。松野トキの記事はこちら
この記事では、小泉セツとはどんな人だったのかをわかりやすく解説します。さらに、生涯や具体的な功績、八雲文学との関わり、そして朝ドラでの描かれ方についても紹介します。
小泉セツ(節子)とは?どんな人だったのか?

小泉セツのイメージ画像
名前は 節子?セツ?
戸籍上は「セツ」、書籍等では「小泉セツ」と紹介されることが多いです。でも本人は「節子」を好んだそうです。そのため著作等では「小泉節子」と書かれています。
生まれは松江
小泉セツ(1868年2月26日~1932年2月18日)は江戸時代から明治に切り替わる慶應4年(明治元年)に生まれました。
家は出雲松江藩の家臣。幼少期から民話や伝承を好む少女でした。
家が没落・苦労を味わう
親戚の稲垣家に養女として引き取られたものの家は没落。わずか11歳で機織工場で働き家計を助けるなど、幼少期から忍耐強く自立した人物でした。結婚と離婚を経験。それを期に姓を実家の「小泉」に戻しました。やがて生活のためにラフカディオ・ハーン(後の小泉八雲)の家で住み込み女中として働き始めます。
ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と出会って結婚
そこで八雲と出会い、まもなく結婚しました。その後、熊本、神戸、東京と転居しながら家庭を築き夫の創作活動を支える重要な役割を担いました。
小泉八雲の執筆を支える
セツは芯が強い女性でした。セツは英語が苦手で、八雲も片言の日本語しか話すことができません。でもセツだけが八雲の話す片言の日本語を正確に理解できました。日本各地の民話や生活知識を語り部として提供しました。こうした支えによって八雲は日本文化を深く理解して執筆活動を行い、代表作『知られぬ日本の面影』『怪談』などの著作が生まれることになりました。
セツは妻というだけではなく、八雲の創作活動を支える重要なパートナーです。彼女の協力が彼の文学に欠かせない存在であったことがわかります。
小泉セツは何をした人?八雲文学を支えた功労者

ラフカディオ・ハーンと小泉セツ
Rihei Tomishige (1837-1922), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で
小泉セツの功績:夫の物語を紡いだ語り部
小泉セツの一番の功績は夫のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に日本の昔話や伝説を語って聞かせたことです。その語りから生まれたのが、八雲の代表作『怪談』をはじめとする数々の名作でした。
語りの才能が八雲の創作を支える
セツは子どもの頃から物語が大好きでした。その記憶から「耳なし芳一」や「雪女」といった日本の怪談や民話をまるでその場面が見えるかのように生き生きと八雲に語りました。
八雲はセツの言葉を通して日本の人々の心や文化の奥深さを知ることができたのです。そして、それを美しい英語で世界に広めました。
八雲にとって欠かせない創作パートナー
八雲はセツを単に情報をくれる人だとは思っていませんでした。彼はセツを創作に欠かせない、大切なパートナーとして心から信頼していました。
後に八雲は自分の本を指して「この本はみんなあなたのおかげで生まれた本です」とセツに感謝の言葉を伝えています。
八雲の日本理解を助けた存在
来日したばかりの頃、日本語も日本の習慣もよくわからなかった八雲にとってセツは日本の文化を知るための重要な窓口でした。セツは八雲を助け日常生活での疑問に答えながら、彼が日本の社会に溶け込み、その内面まで深く見つめる手助けをしました。
夫の人柄を後世に伝えた『思い出の記』
八雲の死後、セツはエリザベス・ビスランドや三成重敬とともに八雲の伝記作りに携わりました。その時の原稿をもとに、後に『思い出の記』という本が出版されました。この本には夫婦の暮らしや八雲の人柄が丁寧に描かれています。
世間では気難しい人だと思われがちだった八雲ですが、じつは無邪気でユーモラスな一面も持っていました。『思い出の記』がなければ、そうした彼の素顔は世の中に知られることなく気難しい姿ばかりが広まっていたかもしれません。
小泉セツの生涯ハイライト

堀から松江城を望む
小泉セツの生涯を簡単にまとめ、年表にしました。
- 1868年(慶応4):松江藩士の家に生まれる
- 幼少期:養女となるも家が没落。
- 1879年(明治12):小学校を卒業。機織工場で働く。(11歳)
- 1886年(明治19):18歳で結婚するも夫が家出。22歳で離婚
- 1891年(明治24):ハーンの家に女中として住み込み、後に結婚
- 熊本・神戸・東京での生活:八雲の著作活動を支え、子どもを育てる
- 1902年(明治35):八雲が『骨董』出版
- 1904年(明治37)4月:八雲が『怪談』出版
- 1904年(明治37)9月:八雲死去
- 1905年(明治38):『思ひ出の記』執筆
- 1906年(明治39):エリザベス・ビスランド『ラフカディオ・ハーン伝記と書簡』に『思ひ出の記』が英訳されて掲載。
- 1914年(大正3):田辺隆次『小泉八雲』に『思ひ出の記』が収録され出版。
- 1932年:64歳で死去、雑司ヶ谷霊園に墓所
64年の生涯の中で八雲との生活はわずか13年。でもその年月はかけがえのないものでした。
晩年と遺したもの
八雲の死後、セツは西大久保の家と書斎を維持しながら子どもたちを育て安定した生活を送りました。『思い出の記』の出版により、八雲との生活や文学活動の裏側を記録として残しました。この記録は、現在も小泉八雲研究や日本文化研究において重要な一次資料とされています。
セツは1932年に64歳で亡くなり、雑司ヶ谷霊園に眠っています。彼女の生涯は、家族を守りながら文化の架け橋となった女性の物語として、多くの人に今も語り継がれています。
朝ドラ「ばけばけ」と松野トキ~小泉セツがヒロインに
2025年放送の朝ドラ『ばけばけ』では、小泉セツをモデルにした松野トキがヒロインに決まりました。松野トキは、幼少期から民話や伝承を好み、困難を乗り越えながら家族や文化を守る女性として描かれています。これは、小泉セツが実際に八雲の創作活動を支え、日本文化を伝えた実像を反映したキャラクターです。
ドラマでは、セツの生い立ちや八雲との出会い、家庭での苦労や文化的貢献などが、フィクションとしてわかりやすく再現されています。視聴者は、セツの実際の人物像を知ることで、松野トキの行動や背景により深い理解を持つことができます。
さらに、ピラー記事内で紹介しているセツの功績や生涯の詳細を知ることで、ドラマで描かれるシーンがよりリアルに感じられるでしょう。ばけばけ:松野トキの記事はこちら
小泉セツの関連書籍・資料
小泉セツは小泉八雲の妻として知られていますが、彼女自身が残した記録や八雲との関わりを描いた著作も存在します。ここでは代表的な関連書籍を紹介します。
『思い出の記』
小泉セツ 著(ハーベスト出版、2024年発行)
小泉セツが夫・八雲との13年8ヶ月にわたる結婚生活を振り返った回想記。
当初はエリザベス・ビスランドとミッチェル・マクドナルドの依頼によって書かれたもの。幼少期からの体験や八雲との出会い、共に過ごした日々が、温かみのある語り口で綴られています。
本書は2025年に発行された新装版。初翻刻となる手記「オヂイ様のはなし」「幼少の頃の思い出」も収録され、新しい注釈とともに読みやすい体裁となっています。
解説を担当した小泉凡氏(セツの曾孫)は、「セツにとって八雲と過ごした時期が最も充実した人生だった」と述べています。
八雲文学を支えた影の功労者としての姿を知る上で必読の一冊です。
『かくも甘き果実』
モニク・トゥルン著(吉田恭子 訳、集英社文庫、2022年発行)
ジョン・ドス・パソス賞を受賞した作家モニク・トゥルンによる長編小説。ラフカディオ・ハーンをめぐる3人の女性――生母ローザ、最初の妻アリシア、そして2番目の妻・小泉セツ――が、それぞれの立場から彼との人生を回想する物語です。小説ですが資料をもとに書かれています。
1909年の東京を舞台に、セツが亡き夫に語りかける姿は創作物語とはいえ彼女の実像を豊かに想像させます。八雲との関係を文学的に読み解く一冊として注目されています。
この本の執筆には参考文献としてエリザベス・ビスランド『ラフカディオ・ハーン伝記と書簡』が活用されています。
小泉セツの関連記事
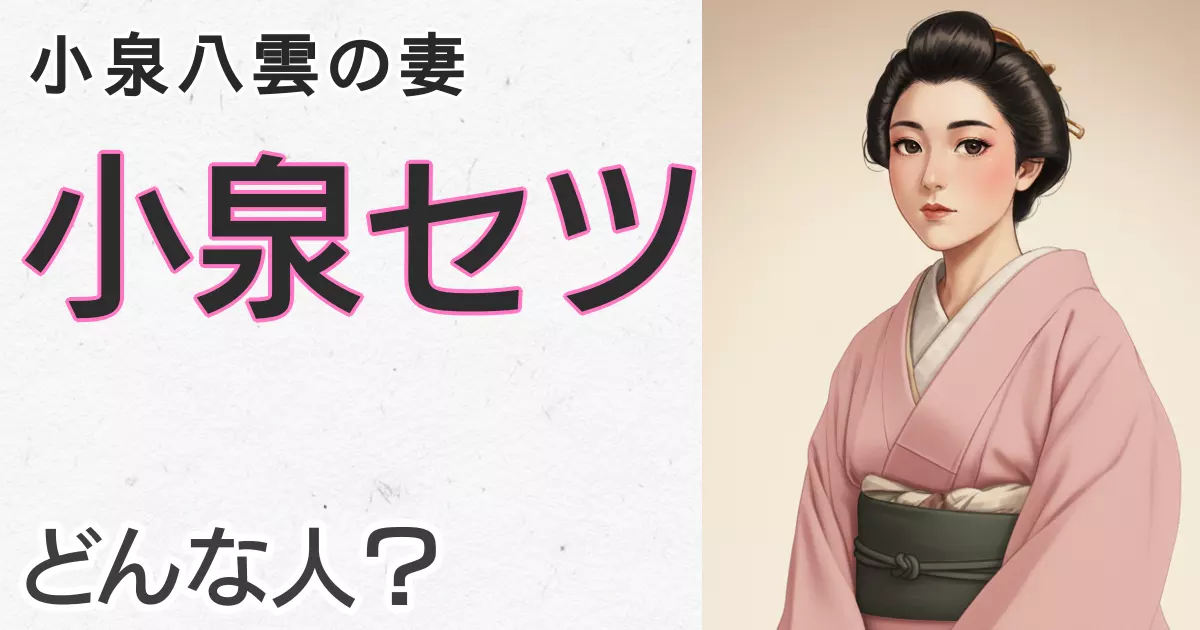


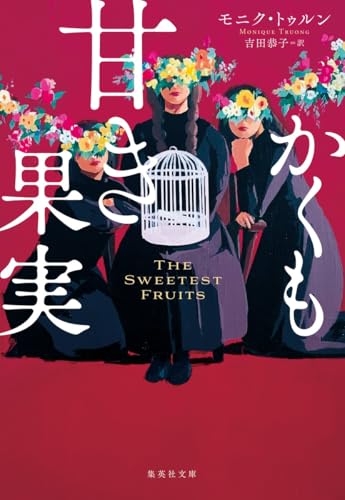
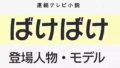
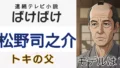
コメント