 7. 江戸時代
7. 江戸時代 赤山靱負(あかやま ゆきえ)・島津斉彬を藩主にしようとしたが自害に追い込まれる
赤山靱負(あかやま ゆきえ)は島津家の分家筋にあたる人物。分家とはいいっても、本家の継ぎに格式の高い日置家の出身です。西郷隆盛の父・吉兵衛が日置家と赤山家の御用人をしていた関係で、隆盛とも縁の深い人物でした。ところが、赤山靱負はお家粗動で切...
 7. 江戸時代
7. 江戸時代  7. 江戸時代
7. 江戸時代  7. 江戸時代
7. 江戸時代  7. 江戸時代
7. 江戸時代  7. 江戸時代
7. 江戸時代  7. 江戸時代
7. 江戸時代 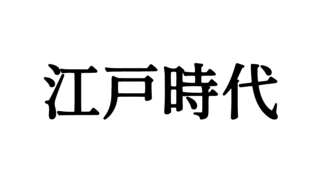 7. 江戸時代
7. 江戸時代 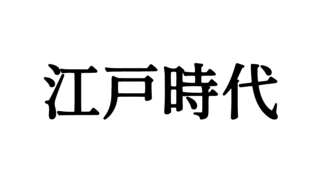 7. 江戸時代
7. 江戸時代 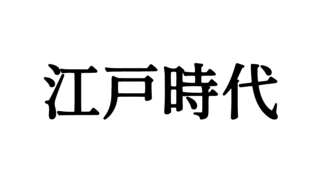 7. 江戸時代
7. 江戸時代 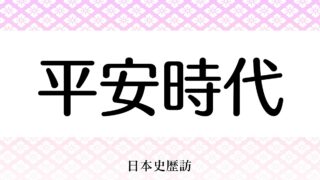 4 平安時代
4 平安時代