江戸幕府13代将軍徳川家定の生母である本寿院は、どんな人生を送ったのでしょうか。
本寿院は大奥で絶大な権力を持ちながらも、その死後は穏やかな生活を選びました。
この記事では本寿院の生涯を追い、彼女の人間性や大奥での影響力、そして幕末の動乱期をどう生きたのかを詳しく解説します。歴史に興味がある人はもちろん、大奥の女性たちの生き方に触れたい人にも役立つでしょう。
本寿院とはどんな女性?基礎知識と生涯の概要
本寿院は江戸幕府13代将軍徳川家定の生母です。彼女は12代将軍徳川家慶の側室でした。将軍の生母として大奥の実権を握ります。しかし家定の死後はその役目を天璋院に譲り、のんびりとした余生を送りました。
本寿院(ほんじゅいん)とは
- 名 前:美津、堅子
- 院 号:本寿院(ほんじゅいん)
- 生 年:文政4年年(1822年)
- 没 年:明治18年(1885年)
- 父:跡部惣左衛門正寧
- 母:不明
- 夫:徳川家慶
- 子:徳川家定、他男2人
旗本の娘から将軍生母へ
文政5年(1822年)、お美津は大奥に入りました。最初は西の丸御次という中級女中です。武士の娘など、コネのある者は御次から始まることがありました。お美津は旗本の娘なので、最初から中級女中だったようです。
文政6年(1823年)、彼女は御中臈(おちゅうろう)になりました。大奥には将軍でもむやみに娘を側室にできない決まりがあります。身分の低い女中を側室にできないのです。将軍や将軍の後継ぎは、気に入った女中がいると、いったん御中臈にさせます。お手がついただけでは側室にはならないのです。
大奥での出世街道 本寿院の駆け上がり方
お美津は将軍の後継ぎである徳川家慶のお手つきとなりました。
御次から御中臈へ 側室となるまで
文政7年(1824年)、お美津は政之助を出産しました。後の徳川家定です。男子を出産した側室はお部屋様と呼ばれます。政之助は乳母の歌橋が養育しました。
文政9年(1826年)と11年(1828年)にも男児を出産しましたが、幼くして亡くなっています。
天保8年(1837年)、11代将軍徳川家斉が将軍職を家慶に譲りました。お美津は将軍の側室となったのです。お美津は他の側室たちとともに本丸大奥へ入りました。
将軍家定の誕生と本寿院の地位確立
お美津の息子である政之助が将軍の後継ぎになりました。お美津は将来の将軍の生母になったのです。これにより「老女上座」の位が与えられました。
翌天保9年(1838年)、将軍家慶の命令で、政之助とともに二の丸大奥に移動しました。
権力者の顔 大奥での本寿院の役割
嘉永6年(1853年)、12代将軍家慶が亡くなりました。お美津は落飾して本寿院と名乗ります。息子の家定が13代将軍となりました。
将軍生母としての影響力
本寿院は将軍の生母となったのです。再び本丸大奥で暮らすようになりました。
安政3年(1856年)、家定の3人目の正室として篤姫がやってきます。家定は体が弱く、後継ぎができませんでした。後継ぎをどうするかという問題が起きていたのです。候補になったのは紀州の徳川慶福と一橋家の一橋慶喜でした。
本寿院たち大奥のほとんどは徳川慶福を支持していました。一橋慶喜は水戸の徳川斉昭の息子です。徳川斉昭は大奥から嫌われていたため、一橋慶喜を支持する者は少数派でした。
徳川斉昭は大奥に倹約を求める一方で、本人には多くの側室がいました。大奥の女中に手を出して問題になったこともあります。本寿院も徳川斉昭を嫌っていました。篤姫と共に大奥に入ってきた幾島は一橋慶喜の支持を増やそうとしましたが、水戸嫌いの大奥を変えることはできません。大奥だけでなく、老中や表の人々も紀州派が優勢でした。
将軍継嗣問題への関与
安政5年(1858年)7月6日、家定が病死しました。14代将軍には本寿院が望んだ通り、徳川慶福が将軍になります。慶福は家茂と名前を変え、14代将軍となりました。
隠居生活の真実 大奥を離れて平穏な日々
家茂が将軍になった後、本寿院は二の丸大奥に移りました。二の丸大奥の規模は本丸大奥の3分の1です。本丸に比べると質素な作りでした。先代将軍の家族が住む場所だったのです。
家定の死後、二の丸大奥へ
天璋院(篤姫)は西の丸大奥に移りました。しかし大御台所として大奥を仕切る天璋院は本丸に戻り、家茂の正室になった皇女和宮と対立します。本丸大奥には他にも家茂の生母である実成院、和宮の生母である観行院もいました。本丸大奥は修羅場のようでした。
でも二の丸で暮らしていた本寿院はこれに関わることなく平穏に過ごしたようです。しかし和宮と対立した篤姫が二の丸に移ってきました。再び天璋院と一緒に暮らすことになったのです。
11月、大奥は火事に見舞われ二の丸が焼けてしまいます。場外の御三卿の家に移りました。西の丸が完成すると本寿院は将軍家茂、和宮、天璋院、実成院とともに移り住みました。
天璋院との対比 平穏な余生
慶応2年(1866年)、長州征伐に出ていた家茂が大坂城で亡くなりました。跡継ぎを巡っても天璋院と和宮は対立したようですが、本寿院は特に関わっていないようです。
15代将軍徳川慶喜は将軍在任中は江戸城に戻らず、正室も京に置いたままでした。天璋院が慶喜の正室の大奥入りを拒んだためですが、慶喜自身も京に行かせる気はなかったようです。そのため天璋院が引き続き大奥を仕切っていました。
大奥の実力者として発言力を維持し続ける天璋院とは対照的に、本寿院は煩わしいことには関わらず、好きなことをして暮らしていたようです。あくまでもマイペースな人だったのです。
明治維新と本寿院 激動の時代を生き抜く
慶応4年(1868年)4月11日、江戸城が開城されました。本寿院は江戸城を出ます。天璋院と一緒に一橋邸に移り住みました。
ここでも徳川家の後継ぎの育成に熱心な天璋院とは対照的に、本寿院はのんびりと余生を送りました。
明治18年(1885年)、本寿院は一橋邸で亡くなりました。享年79歳です。
まとめ
本寿院は徳川家定の生母として大奥で大きな力を持った女性です。
しかし将軍の母という立場にありながらも派閥争いには深入りせず、家定の死後は穏やかな隠居生活を選びました。
激動の幕末を生きた本寿院の生涯は大奥の女性たちが置かれた状況や、彼女たちの人間性がよくわかるでしょう。
この記事が、歴史上の人物「本寿院」への理解を深めるきっかけになれば幸いです。
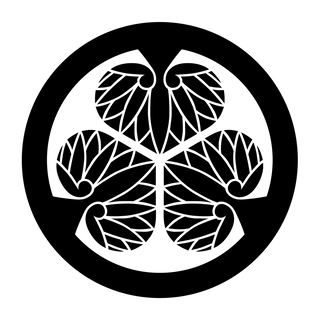

コメント