前回、魏志倭人伝にかかれてある距離から邪馬台国の場所を検証しました。
・邪馬台国の場所はどこ?魏志倭人伝に書かれた距離から調べた結果
今回、魏志倭人伝に書かれている距離以外の地理的な条件から邪馬台国の場所を調べてみたいと思います。
魏志倭人伝の中から方角とかどの方向に何がある。といった条件を調べてだいたいどのへんにあったかというのを明らかにしてみようと思います。
魏志倭人伝にみる邪馬台国の地理的な条件
魏志倭人伝には邪馬台国への道のりが書かれています。
途中までは詳しく分かっています。
| 帯方郡 | 韓国ソウル付近 | 魏の役所所在地 |
|
↓ 7000余里、南に行って東に行く。
|
||
| 狗邪韓国 | 韓国金海市 |
倭の北岸、倭人が住む北限か
|
|
↓ 1000余里、始めて一海を渡る。
(岸沿いではなく海原を進む) |
||
| 対海国 | 長崎県対馬市 | |
|
↓ 1000余里、南の海を渡る。
|
||
| 一大国 | 長崎県壱岐市 | |
|
↓ 1000余里、海を渡る。
|
||
| 末盧国 | 長崎県松浦市 | |
|
↓ 500里、東南、陸路。
|
||
| 伊都国 | 福岡県糸島市 |
代々王がいるが女王国に服属、郡使駐在
|
| ↓ 100里、東南 | ||
| 奴国 | 福岡県福岡市 | |
| ↓ 100里、東 | ||
| 不弥国 | 福岡県宇美町? | |
| ↓ 南 | ||
| 投馬国 | 不明 | |
| ↓ 南 | ||
| 邪馬台国 | 不明 | 女王国 |
|
以下邪馬台国連合の国々
|
||
|
斯馬国、巳百支国、伊邪国、都支国、彌奴国、好古都国、不呼国、姐奴国、對蘇国、蘇奴国、呼邑国、華奴蘇奴国、鬼国、為吾国、鬼奴国、邪馬国、躬臣国、巴利国、支惟国、烏奴国、奴国
|
不明 |
魏の使者がよく知らない国。邪馬台国の北以外にあると思われる |
| ↓ 南 | ||
| 狗奴国 | 不明 |
女王国に従わない
|
さらにこんな条件もあります。
| 女王国より北には国を監視するための一大率(司令官、軍団)を置く。置いてある場所は伊都国。 |
さらに。
| 女王国 |
| ↓1000里、東、海を超える。 |
| 倭人の住む国がある。 |
これらの位置関係から分かることは
- 邪馬台国は伊都国(福岡県糸島市)や奴国(福岡県福岡市)よりも南にある。
- 邪馬台国の南には沢山の同盟国がある。
- さらに南には女王国と対立している狗奴国がある。
- 邪馬台国の東には海がある。その先にも倭人の国がある。
東の海の先の倭人の国と邪馬台国がどのような関係なのかはわかりません。
邪馬台国(邪馬台国)の場所
つまり、邪馬台国の場所はこうなります。
・福岡県福岡市・糸島市より南にある。
・東に海があって、海の向こうには陸地がある。
・南は陸地がある。
となると邪馬台国のあった場所は九州の北部から中部あたりになるんじゃないでしょうか?
現代だと福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、熊本県のどこか?になるかもしれませんね。
東の海は豊後水道と瀬戸内海。南の陸地は宮崎県・熊本県から鹿児島県。と考えれば魏志倭人伝の記述どおりです。
畿内説は地理的条件にあわない
これが畿内説だと「東に海がある」という部分が説明できません。琵琶湖は淡水湖なので海でないことはすぐわかりますし、中国人は琵琶湖を見ても海とは思わないでしょう。畿内の東には東海地方や東国があって陸続きです。
また南の陸地にある国と敵対しているのが説明しにくくなります。
仮に熊野を狗奴国にしたとしたとして。邪馬台国より南にある20~30の同盟国ってどこ?奈良から和歌山の村レベルの集落?となります。
畿内説だと。
邪馬台国連合(奈良)は伊都国(福岡県)に軍隊をおいて北の国を支配下においている。つまり、奈良より北の近畿(大阪・京都・兵庫)から北九州までの地域を支配下においている。当時としては巨大勢力。
それなのに、本拠地(奈良)の近くにある熊野(和歌山)と戦うのに。
魏にわざわざ援軍や仲裁を求めないといけないのか?
という話になります。
東と南を間違えた説は無理がある
また畿内説論者は魏志倭人伝は「南を東と間違えたのだ」と言います。そして東日本の勢力を狗奴国にするのです。
でも魏志倭人伝は「倭人は帯方の東南大海の中にあり」とほぼ正確に日本の位置を理解しています。
日本に来た魏の使者も対海国(対馬)から九州に上陸して福岡にたどり着くまで正確に方角を理解しています。
なのにそこから先に進もうとすると急に方向感覚がおかしくなるのも変な話です。
北九州以外の日本列島では太陽は北から登って真昼に東に来るとでもいうのでしょうか?
南と東を区別できない人間が使者として外国に派遣されることがあり得るのでしょうか?魏の人間は方角も理解できないのでしょうか?
使者が行ったことのない場所は現地人から聞いた内容を書いているとしても、現地人ならよけいに南と東を間違うことはないでしょう。
「南を東と間違えた」説は邪馬台国を畿内に誘致するためのこじつけでしかありません。
そうなるとますます畿内説は厳しいんですよね。
邪馬台国連合は意外と小さい
邪馬台国は魏に使者を送っているし30近い連合国をまとめています。邪馬台国はかなり大きな勢力と思うかもしれません。でも魏志倭人伝を読んでいるとそうではなさそうです。
魏志倭人伝では魏の使者が知っている範囲で倭の地理を説明しています。伝統的に中国の使者は相手国内を見て回り内情を調べるスパイの役目も持っています。邪馬台国連合がどの位の大きさでどの程度の人がいるか、どういう人が住んでいるのかを調べます。全てを見ることはできなかったようですが少なくとも女王国より北は見ることができました。
伝聞で得た知識も含めれば邪馬台国連合がどの適度の規模なのか想定できました。そこで得た知識が魏志倭人伝の邪馬台国の記事になっているのです。
それによると倭の地は海の島にある。島はつながったり、孤立したりしている。
倭の周囲は5000里。
ここで目についたのが倭の地の周囲が5000里と考えていること。
5000里といえば大きいと思うかもしれません。
でも魏志倭人伝の里を機械的にkmに直しても意味はありません。
なにしろ帯方郡(ソウル)~狗邪韓国(金海市)を7000里と書いてるのです。
実際には海路で約700kmです。
さらに魏志倭人伝では以下の距離を1000余里としています。
対馬~金海市(狗邪韓国) 約70km
対馬~壱岐 約60km
壱岐~松浦(末盧国) 約50km
つまり使者の認識は1000里=50~100km
5000里なら300~500km程度。
九州が一周約900kmなので使者が知ってる範囲は九州全土よりも狭いです。邪馬台国連合の支配地域が5000里ということでしょうか?九州の半分が邪馬台国連合に加盟していると考えれば辻褄があいます。
こんなかんじでしょうか?

邪馬台国の範囲
邪馬台国連合は九州の半分ほどの大きさでした。
3世紀の地方国連合ならこのようなものでしょう。
狗奴国相手に20~30の連合国で対抗しているのですから国内でずば抜けて大きな勢力ではなさそうです。
外国に使者を送る勢力が国内最強最大とは限らない
そもそも邪馬台国が倭で最大最強の国とは何処にも書いていません。たまたま魏に使者を送った国というだけです。
「中国の文献に書かれているんだから邪馬台国って凄い国に違いない。」
と、現代人が勝手な思い込みで盛り上がってるだけ。
実は倭にいくつかあった小国家連合の一つだった可能性もあります。たまたま帯方郡に近かったので魏に使者を送った国になれた。というだけなのでしょう。
邪馬台国が日本最大の勢力である必要はないのです。
邪馬台国が魏に使者を送っただけで日本最大の勢力といえるなら。ヨーロッパに使者を送った伊達政宗や大友宗麟は天下人です。「伊達政宗が江戸幕府を作った」と言ってるのと同じです。
とはいえ邪馬台国はその地域では大きな勢力だったのでしょう。それに魏志倭人伝の記述が当時の日本を知る貴重な資料であることも間違いありません。
大きさや場所はともかく、その存在には意義がありますね。
邪馬台国=九州説が有利か
今回は包囲や地理的条件から邪馬台国の場所を考えてみました。
地理的には九州説が有力のようですね。
魏志倭人伝の邪馬台国や卑弥呼の話が本当なら邪馬台国畿内説は厳しそうですね。
僕自身は近畿に住んでいるので心情的には邪馬台国畿内説を応援したい気持ちはありますが。冷静に魏志倭人伝を読んでみると九州にあったように思えるんですね。
仮に魏志倭人伝の内容を無視して、畿内にあった勢力を邪馬台国(ヤマト)と定義、当時の首長を卑弥呼と定義するなら邪馬台国畿内説は成立します。
でも魏志倭人伝を無視するなら、それは現代人の勝手な妄想になってしまいますし。邪馬台国や卑弥呼にこだわる必要はなくなります。ヤマトの成立過程はどうなのか?を先入観なしに調べればいいことです。
また、魏志倭人伝では卑弥呼の国と壱与の国を連続したものと考え首長は同じ一族とみなしてますが。それが間違っている可能性もあります。
同じ一族だったとしても即位した場所が違う可能性もあります。
卑弥呼は九州だけど、壱与は畿内だった。なんてオチもあるかもしれません。
中華王朝からみれば日本列島から来たのだから皆同じと思うかもしれません。でも実は違う地域の代表が勝手に倭の王を名乗って使者を派遣したのかもしれません。
いろいろ解釈できそうです。
今回はお遊びでこんなことを考えてみました。
他にもいろいろ考えてみるのも面白いかもしれませんね。
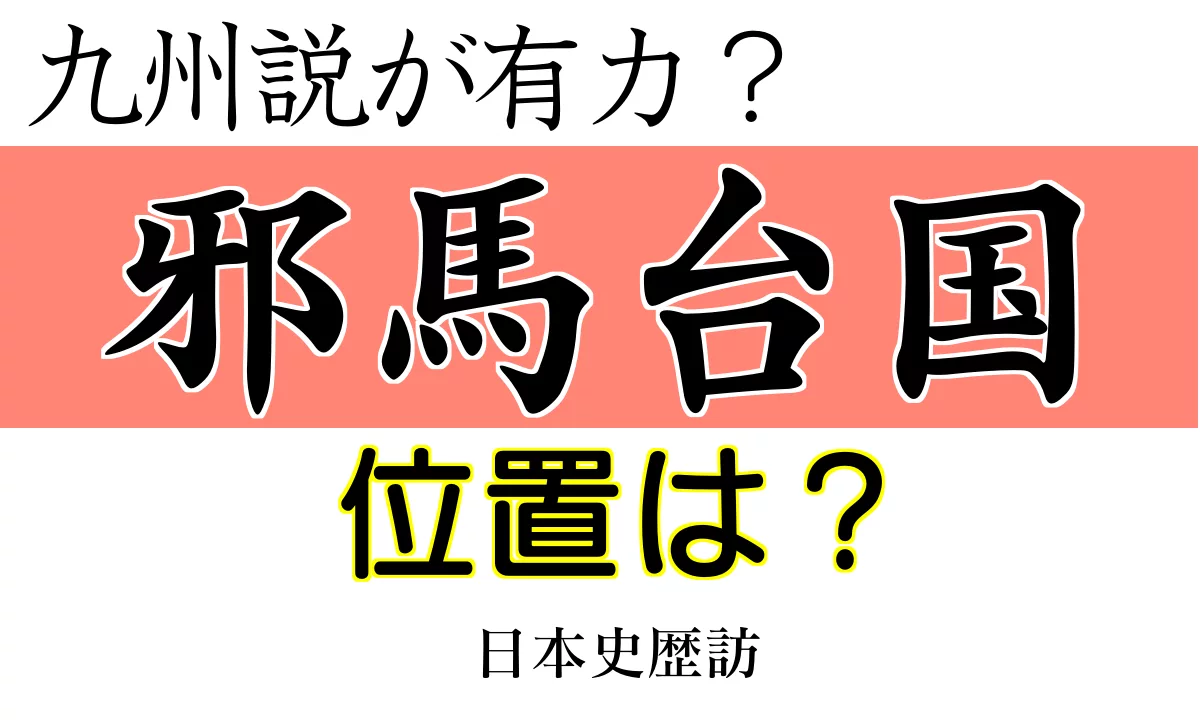
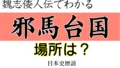
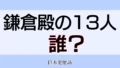
コメント